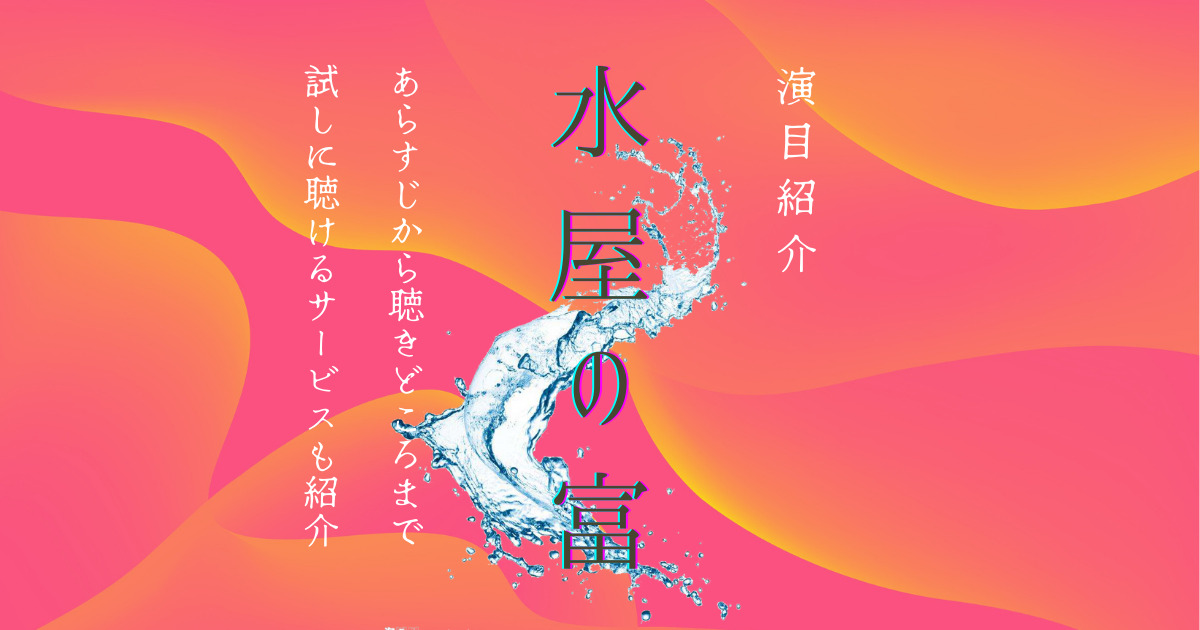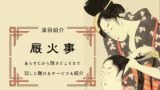日本の伝統芸能「落語」を嗜むうえで知っておきたい名作・定番演目を紹介!
今回は、大金を手にして平静を失った男の右往左往がおもしろい定番演目『水屋の富』(みずやのとみ)について、あらすじや登場人物、楽しむための豆知識をわかりやすく解説します。
記事の最後には、試しに聴いてみるためのサービスも紹介していますので、ぜひご覧ください。
大人の嗜みの入口として「わかった気になる」を応援する情報を発信しています。
日本の伝統芸能「落語」。そこには磨き抜かれた知性と、今も昔も変わらない人間の機微が満ち溢れています。
落語を楽しむことは、江戸の文化や価値観を知ること、人間の滑稽さや強かさ(したたかさ)を再確認すること、人を惹きつける物語や話し方とは何だろうと考えてみること、です。
そんな大人の嗜みとしての「はじめての落語」を応援するため、落語に関する基本的な知識やおすすめの名作落語を、初心者の方にもわかりやすく紹介します。
すぐに『水屋の富』を聴きたい方はすぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービスをどうぞ
『水屋の富』(みずやのとみ)とは?
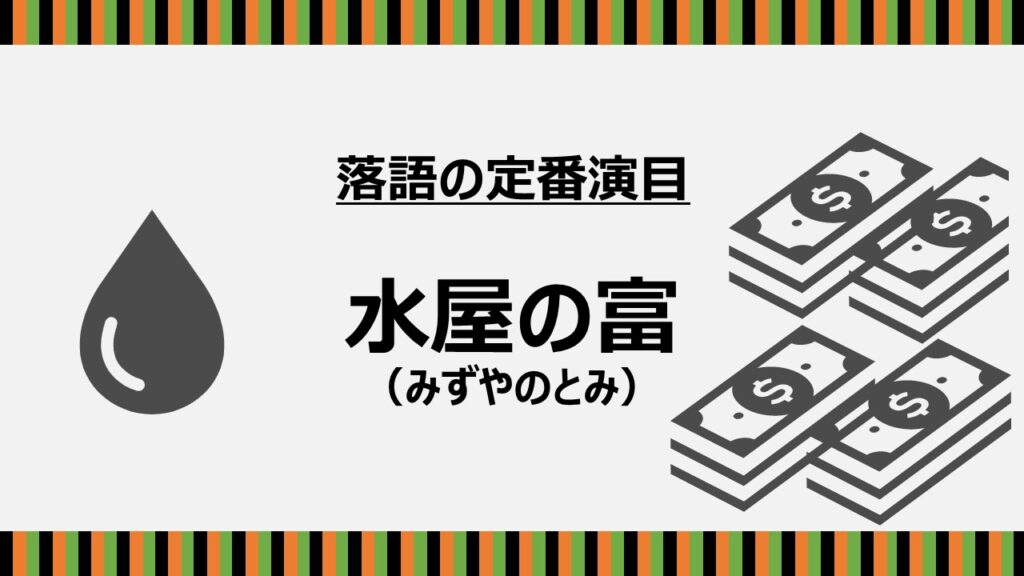
『水屋の富(みずやのとみ)』は富くじを当てて大金を得てしまったために疑心暗鬼に陥る男を描いた滑稽噺です。
思いがけず手にした幸運を、失くしてしまうのではないかと不安になる。そんな人間心理を上手く描いたとても落語らしい演目です。
舞台、登場人物、あらすじ
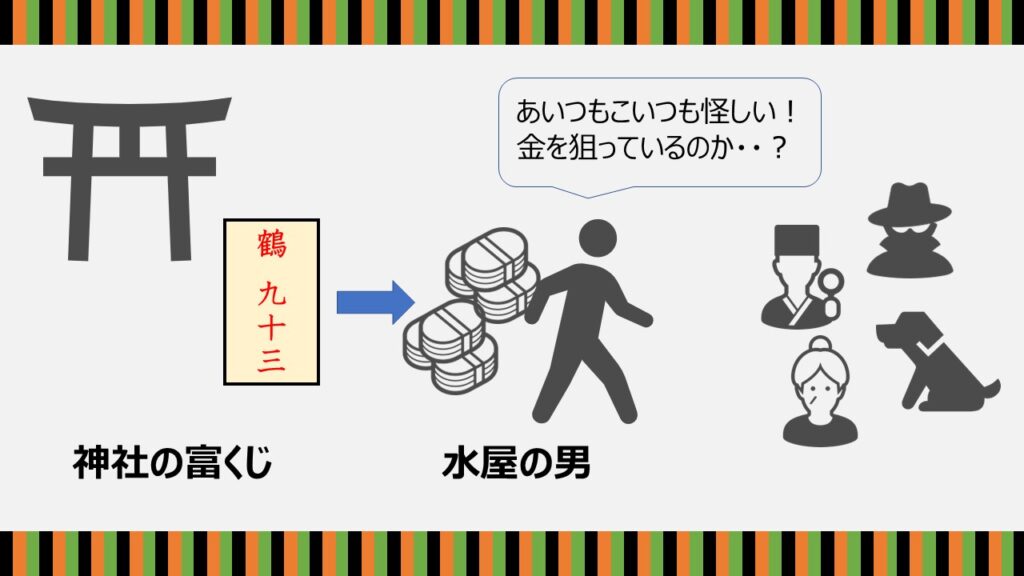
≪舞台≫
・富くじを行う神社
・長屋
≪主な登場人物≫
・水屋の男
・泥棒
≪あらすじ≫
主人公である男は、上水道が届かない地域に飲料水を売り歩く「水屋」として生計を立てていた。儲けの多い仕事ではないため、どうにかまとまったお金が欲しいと考えた水屋は、富くじを購入する。
その富くじがなんと一等に当選し、八百両という大金を手にする。大喜びで長屋に帰ってきた水屋は、人に盗られてはいけないと金の隠し場所を思案する。押し入れの中、神棚の上など色々と検討してみるが、どこも見つかりそうで怖い。あれこれ考えた挙句、畳の下の根太板をはがし、床下の丸太に五寸釘を打ち込んで袋を引っかけて隠すことにする。
その日から、仕事に行こうにも金のことが気になってなかなか出かけられず、夜は強盗に襲われる夢ばかり見てゆっくり眠ることができない。商売にも差し障りが出て、お得意様に小言を言われる。
一方、長屋の隣に住む男は、水屋が毎朝竹竿を縁の下に突っ込み、帰るとまた同じことをするのに気が付いて不審に思う。留守中に忍び込んで床下を暴き、隠してある八百両を見つける。男は、この金を盗んで逃げ出す。
仕事から帰ってきた水屋がいつものように竹竿で縁の下を確かめる。が、手応えがない。根太板をはがして確認したところ、金が盗まれていることに気づく。
≪オチ≫
水屋 「金が盗まれた・・・。これで今晩からゆっくり眠れる。」
落語の入門にはこちらの書籍がおすすめ!

ゼロから分かる!図解落語入門
週刊少年ジャンプで連載中の「あかね噺」もおすすめですよ。

あかね噺 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)
『水屋の富』の聴きどころ
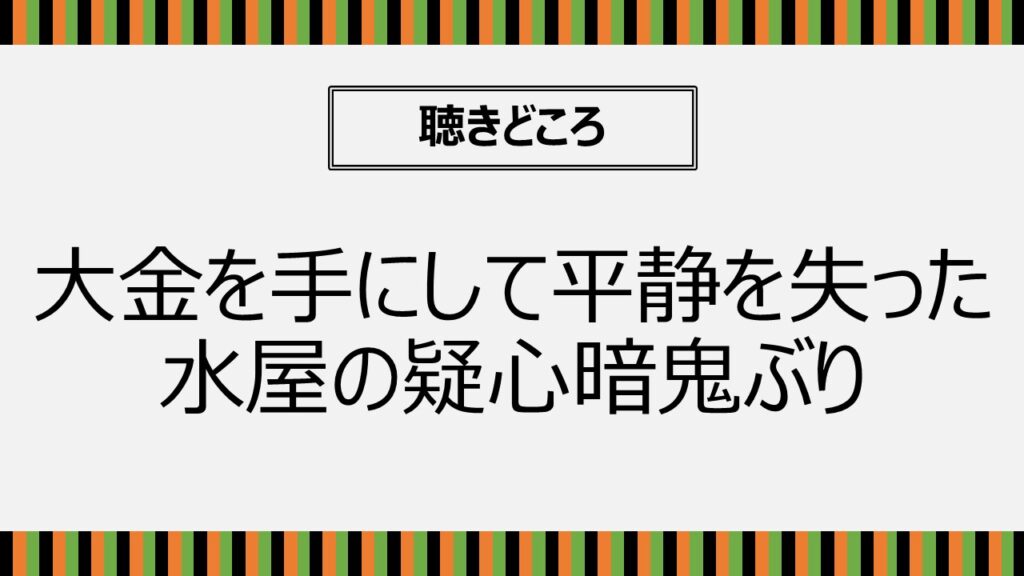
兼好法師は『徒然草』の中で、「財(たから)多ければ身を守るにまどし」と書いています。
思いもかけぬ大金を手にしてしまった水屋が、大金を守るために平静を失っていく様には、今も昔も変わらない人間の愚かさを感じます。
八百両を長屋の部屋に隠そうと思案するも、どうシミュレーションしても(想像上の)泥棒に見つけられてしまう。
水屋という仕事の性質上、大金を得たといってもすぐに辞めるわけにはいきません。代わりの業者を見つけるまでは仕事に行かなくてはいけませんが、大金を家に残して出かけることに不安を抱いているため、家の周りにいる人は大家さんから野良犬まで全員怪しく見えてくる。
何とか仕事を終えて床に着いても、夢の中に強盗や金に困った友人が登場し、あの手この手で八百両を奪おうとしてくる。
そんなことをしているうちにまともに商売ができなくなり、時間通りにお得意様を回れずに小言を言われる・・・。
幸運に恵まれたはずがどんどんノイローゼのようになっていく水屋の様子は、面白可笑しく演じられるので笑いどころではあるのですが、誰しも大なり小なり身に覚えがある姿なのではないでしょうか。

水屋の幸運と不安は、結局は泥棒に八百両を奪われてしまうことで終わります。
家に帰ってきて金が盗まれたことに気付いた水屋が、「今日からゆっくり眠れる」とつぶやくシーンでオチとなります。
大きな幸運を手放してしまったはずが、もうこれで失ってしまう不安に苛まれなくてもよいと胸を撫でおろす。
とても間抜けでありながら、なんとなく気持ちがわかる部分もある。人間の本質的な滑稽さを描いたなんとも落語らしい幕切れといえます。
楽しむための豆知識

『水屋の富』をより楽しむため、背景や噺の中に出てくる言葉をいくつか解説します。
- 水屋
この噺の枕として説明されることも多いですが、江戸時代には「水屋」という商売がありました。
江戸の町は上水道が整った土地ではありましたが、本所や深川などの隅田川の東岸地域には、神田上水や玉川上水は届いていませんでした。
また海岸近くを埋め立てて造られた土地であったため、井戸を掘ったとしても塩分が混ざってしまい、飲料水には適さないものでした。
そのような地域に、桶に入れた飲料水を天秤で担いで売り歩くのが「水屋」という商売です。
元手がかからないため誰でも始められる商売ではありましたが、その売値はかけそば一杯十六文の時代で一荷(二桶)で四文。
大変な重労働であり、また各家庭の飲料水を担うという大きな責任がある割に利益が薄い商売であったといえます。 - 富くじ
今で言う「宝くじ」のこと。
日本の宝くじの歴史は、江戸時代初期に摂津国(現在の大阪府)の箕面山瀧安寺で、正月に参詣した参拝者を対象に抽選で福運のお守りを授けたのが起こりとされています。
その後、当せん品が次第に金銭へと変化し、神社仏閣に限らない様々な組織が、富くじを販売するようになりました。
これを問題視した江戸幕府は富くじに禁令を出しましたが、その後も寺社にだけは修復費用調達の手段として富くじの発売を許しました。特に「江戸の三富」として有名だったのは、谷中の長耀山感応寺、目黒の泰叡山瀧泉寺、湯島天神の富くじ。
現在は一口数百円で買える宝くじですが、当時の富くじは現在の価値で一口数万円という大きな購入資金が必要であったため、庶民の間では、仲間内でお金を出し合って富くじを購入し当選金額は山分けというやり方も一般的だったようです。
すぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービス

今すぐ『水屋の富』を聴いてみたい!という方のために、YouTubeで聴けるもの、音楽配信サービスで聴けるものを紹介します。
特にAmazon Music Unlimitedで聴ける柳家さん喬さんの一席はとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。
YouTube 金原亭龍馬の一席
金原亭龍馬さんのYouTubeチャンネル『金原亭龍馬の落語チャンネル その場しのぎ」より。 様々な場所で収録した高座を配信されており、動画の概要欄には各演目の簡単な解説も記載されていて、これから落語を嗜んでいこうという方には特におすすめのチャンネルです。
Amazon Music Unlimited 柳家さん喬一席
Amazon Music Unlimitedでは、柳家さん喬さんの『水屋の富』を聴くことができます。
特にお金の隠し場所を思案するくだりがとても面白く、終始にやにやしながら聴ける一席となっています。
Amazon Music Unlimitedは、月額定額制の音楽配信サービスですが、最初の30日間無料でお試しできます。
Amazon Music Unlimitedの30日間無料お試しはこちらおわりに

今回は定番演目『水屋の富』について解説しました。
わかった気になっていただけましたでしょうか?
本記事で興味を持っていただけた方は、ぜひ奥深い「落語の世界」に足を踏み入れてみてください。